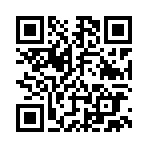虫友に連れられて、ちょうちょの幼生期探し三昧をしてきた。とっても有意義な1日でした。あっ、余韻が残っている。説明はそれぞれの画像に付けてあります。5月13日 大宜味村

















ライマメ(リママメ)収穫。春に比べて豆の肥大は弱い。原因はサシガメの吸汁だ。去年はサシガメ、アブラムシの被害がひどく、終了もわずかだった。これから暑くなるの虫の発生が増えるので、終了が減るのは覚悟している。5月10日中城村







花壇に植えたダイズの生育を良くするため除草をしていたら、大事(ダイズ)な葉をタテハチョウ科リュウキュウミスジの終令幼虫が食んでいた。どうするべき。5月3日中城公園

マメ科クロヨナが咲いた。去年は確か6月頃だったと思うが、今年は5月はじめ、蕾もたくさん。どうやらクロヨナ年に2回開花するようだ。5月2日中城公園

アカショウビンの鳴きを聞いたのでそろそろアサギマダラが飛来してくると踏んでいたら、今朝2 捕獲してマーキングすることが出来た。4月29日中城村
捕獲してマーキングすることが出来た。4月29日中城村
 捕獲してマーキングすることが出来た。4月29日中城村
捕獲してマーキングすることが出来た。4月29日中城村
久しぶりにタテハチョウ科アカボシゴマダラを見たいと思い訪ねたら、雄のテリトリー争いをしていた。そのため撮影は難しかった。やっと1枚撮れたが、ピンがかなり甘い。4月22日中城村

今年は、ちょうちょの成虫と同じように幼虫たちもなかなか見つからない。今日はようやくセセリチョウ科オキナワビロウドセセリの幼虫をマメ科クロヨナで、テングチョウの幼虫をアサ科クワノハエノキで見つけることが出来た。これからも続いて欲しいなー。4月9日中城村



アカボシゴマダラはベトナム・中国・台湾・朝鮮半島に、国内では奄美諸島に奄美亜種が在来分布、埼玉・神奈川県には別亜種が移入由来で生息している。
沖縄島での記録は1890年代。それ以降1950年代には奄美群島の固有亜種と考えられていた。記録はないのか様々な資料を探したが見つからなかった。1900年以降の確かな記録はないようだ。
北中城村では2024年8月12日3 を皮切りに、10月22日まで成虫が撮影と採集がされて、幼虫・蛹をアサ科クワノハエノキで撮影・観察された。本種が沖縄島に定着するか、その後の同行が気になっていたら、4月4日に成虫を撮影することが出来た。
を皮切りに、10月22日まで成虫が撮影と採集がされて、幼虫・蛹をアサ科クワノハエノキで撮影・観察された。本種が沖縄島に定着するか、その後の同行が気になっていたら、4月4日に成虫を撮影することが出来た。
沖縄島での記録は1890年代。それ以降1950年代には奄美群島の固有亜種と考えられていた。記録はないのか様々な資料を探したが見つからなかった。1900年以降の確かな記録はないようだ。
北中城村では2024年8月12日3
 を皮切りに、10月22日まで成虫が撮影と採集がされて、幼虫・蛹をアサ科クワノハエノキで撮影・観察された。本種が沖縄島に定着するか、その後の同行が気になっていたら、4月4日に成虫を撮影することが出来た。
を皮切りに、10月22日まで成虫が撮影と採集がされて、幼虫・蛹をアサ科クワノハエノキで撮影・観察された。本種が沖縄島に定着するか、その後の同行が気になっていたら、4月4日に成虫を撮影することが出来た。
とっても久しぶりにタテハチョウ科コノハチョウの幼虫を観察してきた。セイタカスズムシソウの群生地に行くと、木漏れ日の中、成虫が日光浴。見つけて動いた瞬間、飛んで行ってしまった。付近を捜索、幼虫がいたのは葉裏。食痕らしきがあったので、捜索をはじめて30分ほどで発見。若~中令まで6頭だった。4月7日本部町



公園に育つソテツの新葉にシジミチョウ科クロマダラソテツシジミ幼虫19頭を見つけた。どうやら冬越しが成功したようだ。数年のうちには定着宣言が出るのかもしれないな。3月21日浦添市

「ちょうちょがいない」「少ない」、何十年と観察を続けているがはじめて。で、昨日シロオビアゲハがサシグサ、今日チャバネセセリがシャリンバイに訪花していた。これから毎日がちょうちょの日になることを臨む。3月30日中城村



11月中旬に播種したツタンカーメンエンドウは、本日莢を初収穫した。例年だと10月下旬播種だが、猛暑で遅れた。それでも成長に最適な涼しい気候が長く続き、順調に生育、今年も豊作だ。いつもなら1月中旬頃からの収穫開始だったが、だいぶ遅れた。まあ、こんな年もあるのかなと思う。知人から種譲り受けてから11年目を迎えた。種用を採取保管し、今年もたくさんの方々配りたいと思う。



クチナシで染めたご飯は炊くときにサンニン(ゲットウ)生葉を入れて炊き、蒸らすときに追いサンニンをしたので香りがとっても良かった。キマメご飯は、シソアオイ葉を乾燥させてつぶし混ぜこんでのおにぎりだった。酸味とキマメの風味が良かった。食べ過ぎだー。

キマメを収穫した。豆ご飯にする予定、楽しみだ。このキマメ、数年前知人から種をもらって播種、鉢植えで育ててきた。試しにと食べたら美味しい。これは大きく成長させたらム収量が見込めると思い。去年の3月29日に播種、発芽し4月2日前後。莢が付き始めたのは11月20日前後から。そした収穫は年が開けたら数回行ってきた。このところ、莢に入っている豆の肥大が顕著で一度にたくさん収穫出来るようになってきた。あと何回採れるのだろう。2月5日中城村





マメ科ワニグチモダマの花にセイヨウミツバチが訪花。花は沢山咲くけど莢は見かけない問題。ハチでの受粉が成功すれば莢がつき大好きな種子が付くことになる。これは期待できるなー、と妄想。1月26日やんばる

モモ(キームム)の台木にスモモ、ヒカンザクラの台木にヒカンザクラ白花の接ぎ木をした。毎年、大寒の頃行っている季節の作業。今年の結果はどうなるのかは「ウデ」が健全か否の判断になる。失敗だと修行のやりなおしだ。

栽培中のマメ科植物途中経過。ツタンカーメンエンドウは開花が始まった。去年の猛暑で播種が半月程遅れたので、開花も遅かった。キマメは鉢植えから露地上に変更、たくさんの花が咲き、莢が沢山ついている。先んじて完熟した莢が2個あった。まとまって収穫できるのはもっと先のようだ。1月8日中城村
ツタンカーメンエンドウの花

キマメ完熟豆と若莢

ツタンカーメンエンドウの花

キマメ完熟豆と若莢